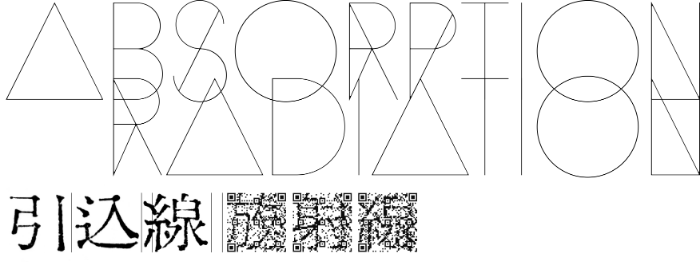基本的な話からはじめよう。私たちが存在する世界の根源的な要素である原子が不安定なむすびつきの状態にあるとき、それが安定した状態へと移り変わろうとする過程において、放射線──粒子線と電磁波の総称──は放たれる(それを、放射性崩壊という)。この変化は元素ごとに定まった確率のもとで起こり(それを、半減期という)、場合によっては何度も繰り返される。より特殊な例においては、不安定な原子は自ら分裂し(それを、自発核分裂という)、他の安定した原子をも分裂させるほどの影響と干渉をもたらすことがある。
原子爆弾や原子力発電は、それら核物理の現象における一部分──集約された運動エネルギーによって発生する膨大な熱量──に注目し、人間が介入と操作を行うことによって成立する設計的な力である。八年前の出来事は、この力が破綻したことによってもたらされた。
1945年の夏以後、あるいは2011年の春以後、「放射線」という言葉は私たちの歴史に挫折として刻まれ、今なおある種の禍々しさを放ち続けている。原子爆弾をひとつの契機として作られてきた戦後の枠組みは、福島第一原子力発電所の事故をひとつの契機として大きく変わろうとしている。原爆が国家神話を崩壊させたとき、あるいは原発事故がテクノロジーによる進歩の神話を崩壊させたとき、私たちは、それまでドグマによって覆われていた「現実的な」物理的世界を垣間見ることになった。「放射線」を志向することは、そうした不安定な場に立ち続けることを意味するだろう。
〈引込線/放射線〉というプロジェクトは、原子が放射線を放つことによって安定へと向かう一連のプロセスに、「原子力」ではないものを見いだす試みである。不安定な原子がエネルギーを放出しながら存在を変えてゆくように、さまざまな衝動を抱えて生きる人間たちは、何らかの表出行為によって常に別の何かに変わっていく可能性に晒され続けている。そして私たちは、ほとんどの場合、この変容がいつどのように起こるかを予測できない。もちろんこれは、放射性元素とのアナロジーである。放射性元素の個々の原子の振る舞いは確率的で、最終的に安定した同位体へ至るにせよ、分裂や崩壊がいつ起こるかを前もって知ることは不可能だ。しかし、そうした元素が十分な量をともなって現れるなら、それがどのように変化していくかは測定可能なものとなる。では、人間はどうだろうか。さまざまな個人が不安定なままに集い、あるまとまり──家族や共同体や国家、あるいは、展覧会やアート・コレクティブや〈引込線/放射線〉といったプロジェクト──を形づくることで、放射性元素のように一定不変の物理法則に至らずとも、その全体としての振る舞いは十分に安定したものとして継続的な考察の対象となるはずである。
重要なのは、個々の質、そして量という全体を、再帰的な関係において捉えることである。例えば、美術館という機関がなぜ必要なのかを考えてみよう。私たちは、ある物象や事象が美術(ないし芸術、あるいはアート)であるか否かを、それ単独に対して判断できない。多くの事象や物象が集まり十分な量をなすことで、初めてそれに対する妥当な価値判断が可能になる。つまり、個々の事象や物象に対する価値判断と、個々を支え包摂する全体が想定されること(それ自体ひとつの価値判断である)とは、相互形成的なのである。美術館は、すでに価値づけられたものを収める場としてだけでなく、未だ価値づけられていないもの(の集まり)から生み出されるマトリックスとしても、必要なのである。
〈引込線/放射線〉プロジェクトの前身──あるいは母体(マトリックス)──である「引込線」は、歴史的に、1952年の国立近代美術館(現・東京国立近代美術館)開館以後の「戦後美術」における、オルタナティブな制作/発表の諸実践を引き継ぐものと言えるだろう。特に、1980年代以降急速に広まった野外彫刻展は、その直接の源流である。こうした一連の動きを、近代美術館的なキュレーションによる「選択と集中」と、オルタナティブかつ非キュレーション的な「制作の蓄積」の分裂として捉えることも可能だ。それは、同じく1952年のヴェネチア・ビエンナーレへの参加に始まる「国際派」と、それがオミットし続けた公募美術団体に代表される「国内派」との分裂でもある。国際展を最終的なアウトプットと想定する戦後の「国際派」は、画壇制度に基盤を持つ「国内派」を否定──ないし否認──した。その一方で近代美術館的なキュレーションは、多くの批判に晒されながらも戦前から継続している公募美術団体による「制作の蓄積」に依存してもいたのだ。こうして生まれた日本の「現代美術」は、「日本的なもの」へのアンビバレンスを抱える「国際派」と、ドメスティックな制度に閉じこもる「国内派」との不毛な対立を抱え続けることになる。
こうした対立ないし分裂状態が、そもそも回避されるべきものだったか否かは一概に言えないが、現にここにある以上、それを回避しようとする試みが問題解決への方途にならないのは明らかだ。分裂状態にある全体を吟味し、思考し、記述すること、そうすることを許容するだけの量を確保すること、量としての全体の現れを阻害するフレームワークに揺さぶりをかけること、そして、そのための場を作り、維持・改良し続けること、そうしたことが求められている(ただし、その量なるものはいかなるフレームもなしに見いだされうるものなのか、という認識論的な問いは当然あるだろう。「国家」こそが最も強力なフレームワークとしてしばしば作用するとも言えるからだ)。十分な量を欠いた状態での「選択と集中」──それを「原子力」的なキュレーションと呼んでもよい──は、偶然を必然と取り違える(ことで、確率的なものを確定的なものと錯誤する)危険と背中合わせである。そのような取り違えが拾い上げたものを、とりあえず破線状に並べただけのものを、はたして私たちは「歴史」と呼べるのだろうか?私たちの「戦後美術」、そして「現代美術」は、そうした破線ですらなく、足踏みの痕跡に過ぎないのではないだろうか?
〈引込線/放射線〉プロジェクトは、不安定な人間たちがさまざまな経路から数多く集い、互いを無秩序な変化や影響に晒しだす場を共有し、そのあり様をそのまま提示するものである。そうであれば、その場へ何かを求めて訪れる「安定した」状態にある人間(鑑賞者)たちもまた、無関係な傍観者でいることはできない。キュリーとフレデリックの実験から原子炉内の核分裂まで、不安定な元素から放射されるエネルギーの流れは、安定的だった元素も同様に不安定なものへと変えてしまう可能性を持つ(それを、放射化という)。この可能性は、美術(ないし芸術、あるいはアート)において、しばしば感染のメタファーで語られてきたが、もちろんこれは一方通行のものではないし、また、閉じた場で営まれるものでもない。
〈引込線/放射線〉は、その名称が示すように、「引き込む」ことと「放射する」ことを重ね合わせながら/入れ替えながら思考し実践する運動体である。「引き込む」ことで形づくられる全体(という量)と、そこから/そこへ「放射する」ものとしての個(という質)は、等しく再帰的なものとして理解されるべきなのだ。そうであればこそ、個は特殊な例外としてではなく、いずれ──それがいつになるかはわからないとしても──全体を構成することになるだろうユニークな一プレーヤーとして、自身の不安定な存在の(確率的な)条件を享受できるのだ。そして、そうすることによってのみ、動的でありつつ安定した「歴史」が生き生きとしたものとして共有される。〈引込線/放射線〉というプロジェクトが今日存在しようとする意義は、そこにこそ見いだされるはずである。
[R. T. +T. M. ]
《ひとつではなく、複数のステイトメントを掲げ、散らす》2019、〈引込線/放射線〉実行委員会
基本的な話からはじめよう。私たちが存在する世界の根源的な要素である原子が不安定なむすびつきの状態にあるとき、それが安定した状態へと移り変わろうとする過程において、放射線──粒子線と電磁波の総称──は放たれる(それを、放射性崩壊という)。この変化は元素ごとに定まった確率のもとで起こり(それを、半減期という)、場合によっては何度も繰り返される。より特殊な例においては、不安定な原子は自ら分裂し(それを、自発核分裂という)、他の安定した原子をも分裂させるほどの影響と干渉をもたらすことがある。
原子爆弾や原子力発電は、それら核物理の現象における一部分──集約された運動エネルギーによって発生する膨大な熱量──に注目し、人間が介入と操作を行うことによって成立する設計的な力である。八年前の出来事は、この力が破綻したことによってもたらされた。
1945年の夏以後、あるいは2011年の春以後、「放射線」という言葉は私たちの歴史に挫折として刻まれ、今なおある種の禍々しさを放ち続けている。原子爆弾をひとつの契機として作られてきた戦後の枠組みは、福島第一原子力発電所の事故をひとつの契機として大きく変わろうとしている。原爆が国家神話を崩壊させたとき、あるいは原発事故がテクノロジーによる進歩の神話を崩壊させたとき、私たちは、それまでドグマによって覆われていた「現実的な」物理的世界を垣間見ることになった。「放射線」を志向することは、そうした不安定な場に立ち続けることを意味するだろう。
〈引込線/放射線〉というプロジェクトは、原子が放射線を放つことによって安定へと向かう一連のプロセスに、「原子力」ではないものを見いだす試みである。不安定な原子がエネルギーを放出しながら存在を変えてゆくように、さまざまな衝動を抱えて生きる人間たちは、何らかの表出行為によって常に別の何かに変わっていく可能性に晒され続けている。そして私たちは、ほとんどの場合、この変容がいつどのように起こるかを予測できない。もちろんこれは、放射性元素とのアナロジーである。放射性元素の個々の原子の振る舞いは確率的で、最終的に安定した同位体へ至るにせよ、分裂や崩壊がいつ起こるかを前もって知ることは不可能だ。しかし、そうした元素が十分な量をともなって現れるなら、それがどのように変化していくかは測定可能なものとなる。では、人間はどうだろうか。さまざまな個人が不安定なままに集い、あるまとまり──家族や共同体や国家、あるいは、展覧会やアート・コレクティブや〈引込線/放射線〉といったプロジェクト──を形づくることで、放射性元素のように一定不変の物理法則に至らずとも、その全体としての振る舞いは十分に安定したものとして継続的な考察の対象となるはずである。
重要なのは、個々の質、そして量という全体を、再帰的な関係において捉えることである。例えば、美術館という機関がなぜ必要なのかを考えてみよう。私たちは、ある物象や事象が美術(ないし芸術、あるいはアート)であるか否かを、それ単独に対して判断できない。多くの事象や物象が集まり十分な量をなすことで、初めてそれに対する妥当な価値判断が可能になる。つまり、個々の事象や物象に対する価値判断と、個々を支え包摂する全体が想定されること(それ自体ひとつの価値判断である)とは、相互形成的なのである。美術館は、すでに価値づけられたものを収める場としてだけでなく、未だ価値づけられていないもの(の集まり)から生み出されるマトリックスとしても、必要なのである。
〈引込線/放射線〉プロジェクトの前身──あるいは母体(マトリックス)──である「引込線」は、歴史的に、1952年の国立近代美術館(現・東京国立近代美術館)開館以後の「戦後美術」における、オルタナティブな制作/発表の諸実践を引き継ぐものと言えるだろう。特に、1980年代以降急速に広まった野外彫刻展は、その直接の源流である。こうした一連の動きを、近代美術館的なキュレーションによる「選択と集中」と、オルタナティブかつ非キュレーション的な「制作の蓄積」の分裂として捉えることも可能だ。それは、同じく1952年のヴェネチア・ビエンナーレへの参加に始まる「国際派」と、それがオミットし続けた公募美術団体に代表される「国内派」との分裂でもある。国際展を最終的なアウトプットと想定する戦後の「国際派」は、画壇制度に基盤を持つ「国内派」を否定──ないし否認──した。その一方で近代美術館的なキュレーションは、多くの批判に晒されながらも戦前から継続している公募美術団体による「制作の蓄積」に依存してもいたのだ。こうして生まれた日本の「現代美術」は、「日本的なもの」へのアンビバレンスを抱える「国際派」と、ドメスティックな制度に閉じこもる「国内派」との不毛な対立を抱え続けることになる。
こうした対立ないし分裂状態が、そもそも回避されるべきものだったか否かは一概に言えないが、現にここにある以上、それを回避しようとする試みが問題解決への方途にならないのは明らかだ。分裂状態にある全体を吟味し、思考し、記述すること、そうすることを許容するだけの量を確保すること、量としての全体の現れを阻害するフレームワークに揺さぶりをかけること、そして、そのための場を作り、維持・改良し続けること、そうしたことが求められている(ただし、その量なるものはいかなるフレームもなしに見いだされうるものなのか、という認識論的な問いは当然あるだろう。「国家」こそが最も強力なフレームワークとしてしばしば作用するとも言えるからだ)。十分な量を欠いた状態での「選択と集中」──それを「原子力」的なキュレーションと呼んでもよい──は、偶然を必然と取り違える(ことで、確率的なものを確定的なものと錯誤する)危険と背中合わせである。そのような取り違えが拾い上げたものを、とりあえず破線状に並べただけのものを、はたして私たちは「歴史」と呼べるのだろうか?私たちの「戦後美術」、そして「現代美術」は、そうした破線ですらなく、足踏みの痕跡に過ぎないのではないだろうか?
〈引込線/放射線〉プロジェクトは、不安定な人間たちがさまざまな経路から数多く集い、互いを無秩序な変化や影響に晒しだす場を共有し、そのあり様をそのまま提示するものである。そうであれば、その場へ何かを求めて訪れる「安定した」状態にある人間(鑑賞者)たちもまた、無関係な傍観者でいることはできない。キュリーとフレデリックの実験から原子炉内の核分裂まで、不安定な元素から放射されるエネルギーの流れは、安定的だった元素も同様に不安定なものへと変えてしまう可能性を持つ(それを、放射化という)。この可能性は、美術(ないし芸術、あるいはアート)において、しばしば感染のメタファーで語られてきたが、もちろんこれは一方通行のものではないし、また、閉じた場で営まれるものでもない。
〈引込線/放射線〉は、その名称が示すように、「引き込む」ことと「放射する」ことを重ね合わせながら/入れ替えながら思考し実践する運動体である。「引き込む」ことで形づくられる全体(という量)と、そこから/そこへ「放射する」ものとしての個(という質)は、等しく再帰的なものとして理解されるべきなのだ。そうであればこそ、個は特殊な例外としてではなく、いずれ──それがいつになるかはわからないとしても──全体を構成することになるだろうユニークな一プレーヤーとして、自身の不安定な存在の(確率的な)条件を享受できるのだ。そして、そうすることによってのみ、動的でありつつ安定した「歴史」が生き生きとしたものとして共有される。〈引込線/放射線〉というプロジェクトが今日存在しようとする意義は、そこにこそ見いだされるはずである。
[R. T. +T. M. ]
《ひとつではなく、複数のステイトメントを掲げ、散らす》2019、〈引込線/放射線〉実行委員会