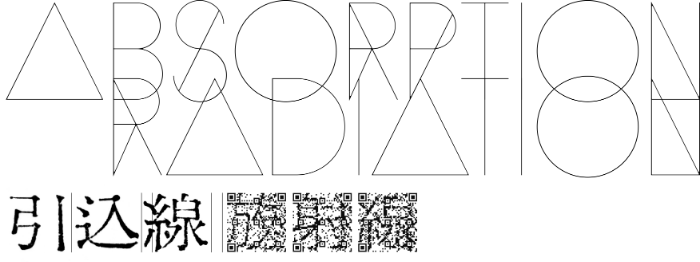2009年の第一回展からビエンナーレ形式で開催されてきた引込線が十年目の節目を迎えた。名称を〈引込線/放射線〉と変更した本プロジェクトは、設立当初より掲げてきた「ノン・テーマ、ノン・キュレーション」の活動方針を刷新する改革期にある。
残された唯一の枠組みは、既存の制度に拠らないオルタナティブな自主企画展=セルフキュレーションであるということ。本プロジェクトの準備段階では実行委員会を組織して会合を重ね、この枠組みを問い直し、壊し、仮設する作業を幾度となく繰り返してきた。
会合はさながら小さな議会の様相を呈し、実行委員である三十余名の参加者全員が投票権を有して共同体の意思決定に関わる直接民主主義的な体制をとった。プロジェクトにまつわる重要案件は、議案の提出と採決を経てはじめて実行に移すというシステムである。全員が〈引込線/放射線〉を動かしうる権限を持つということ。つまり、ノン・キュレーションは汎キュレーション(pan-curation)の可能性へと通じたのだ。
「緩やかな集い」を前提とする従来の〈引込線〉は、同質性で結び付いた閉鎖的な共同体と見做されることも少なくなかった。しかし実際のところはどうか。「緩やか」という形容は決して正確ではない。異なる思想、異なる背景を持つ者たちの必然性を欠いた集まりは、具体的な問題に直面するたびに、意見の相違、衝突、軋轢といったものを避けがたく生み出してきた。ディスコミュニケーション、付和雷同、宙吊りのまま放置されたアイデア──、負の要素が蓄積するなかで、合意へ到るまでの穏当な手続きが、いつの間にか熾烈な闘争へと転化する。セルフの暴走。綱領なき集団が、各々の目論見を遂行しながら集団性を維持することは果たして可能か。
1909年の創立宣言以降、数多くのマニフェストを発布してきた未来派は、「我々」という主語の扇情的な使用を大いに好んだ。運動の中心人物F・T・マリネッティが目指したのは、伝統的な詩法が依拠する統語法を破壊して「私」なる主語を解体することだった。
他方、過剰なまでに繰り返し用いられた「我々」なる主語は、ひとつの党派の連帯を押し進めると同時に、「我々」と「奴ら」、「味方」と「敵」の分断をもたらした。前衛主義が排他的なエリーティズムに終始するとき、その革命が持ちえたはずの真の波及力は失われる。
「我々」を構成するものとは何か。〈引込線/放射線〉のような綱領なき集団ならば尚更、この主語を無反省に用いることはできない。解体すべきは「我々」という一人称複数形がもたらす有無を言わさぬ拘束力である。
「私」であり「あなた」でもあり「彼/彼女」でもある「誰か」。上下左右の区別もなく、「我々」の強固なまとまりから逃れて幾つもの人称が湧出するとき、分断線は取り払われ、我も彼もが激しく接触する混戦状態が実現する。
個々がセルフィッシュに振る舞いながら、それぞれの卓越性をそれぞれの仕方で追求し、ときには他の誰かの能力を引き出すために連携を仕掛け、(不)自由と(無)責任、緊張と弛緩の極を揺れ動く不断のゲームを進行させること。ルールの形成と破壊を繰り返していく闘争は、やがて一種のスポーツに似たものへと変貌するだろう。
汎キュレーション(pan-curation)の響きから転じてパンクラチオン(Pankration)へ。古代オリンピックの正式種目だったこの格闘技が、目潰しや噛みつき以外なら何でもありの野蛮な競技だったことを記しておこう。あるいはここで、観客と演者の激しい応酬が繰り広げられた「未来派の夕べ」を思い起こしてもよいかもしれない。「夕べ」の舞台では、観客が演者を野次り、果物やパスタを投げつけ、ときに殴り合いの暴力沙汰にまで発展することがあった。「書物に対する体操の優位」を謳った未来派は、幾つかの宣言内にスポーツのメタファーを散りばめている。「未来派の舞台は、我々の競争精神を鍛える競技場となるだろう」(「未来派総合演劇宣言」、1915年)。それから数十年後、美術評論家のH・ローゼンバーグは、抽象表現主義の画家たちのキャンバスを「行為(アクト)する場としての闘技場」になぞらえたのだった(「アメリカのアクション・ペインターたち」、1951年)。アクションの場はこれまでも、地域、時代、文脈、物理的空間を超えて次々とスプリットしてきたのである。
十九世紀後半に興隆した近代スポーツは、ルールを整備することで公平性(フェアネス)を確保し、プロフェッショナル/アマチュア、貴族階級/労働者階級の分断を取り払って参加の機会の平等を促した。著名な社会学者の説を借りれば、近代スポーツの誕生は、暴力が抑制されて社会が文明化していく過程、民主主義的な議会政治の成立と軌を一にしている。スポーツとは元来、戦争に代わる闘争のモデルである。
とはいえ、いくら制度が確立されたところでスポーツの世界に不正や不備はつきものである。同様に、ルールで保証される民主主義的な機構の限界は、〈引込線/放射線〉の小さな議会がたびたび直面してきたことでもある。疑うべきは、公平性(フェアネス)の幻想とあらゆる差異を隠蔽する穏健な個人主義なのだ。安定がどこにもないことを受け入れた上で、闘争のモードを維持しながら、なおかつそのモードを駆動させる基盤自体を批判的に読み替えていく必要がある。スポーツとも芸術とも名づけがたい闘争の場で、〈引込線/放射線〉のプロジェクトは不穏なアクションを続けていくと予告しよう。
闘技場(アリーナ)はひとつとは限らない。シーズンを通じて、複数の場所で、同時多発的に、あるいはディレイを伴いながら、予定調和な筋書きを廃棄した幾つものプレイが実行されるだろう。ひとりのパフォーマーの生身、色面に覆われたキャンバス、印刷物、仮想空間、複数に並立するステイトメントすらも闘争の場となるのだ。そこではルールを逆手にとったぺてんやいかさまが横行し、フィールドに迷い込んだ動物がゲームを中断させ、無法者(フーリガン)の乱入によって暴動が引き起こされることもありうるだろう。数的な強みを活かしたチームプレイと一切の外野を無視した個人プレイを行き来するなかで、勝利と敗北、成功と失敗が重ね合わせの状態で同時に存在することもありうるだろう。
有線、無線、断線、死線。引き込み放射する幾筋もの軌跡。セルフを超えて、保証のない未来に向けて、様々な諸力がひしめく集団的発明物としての〈引込線/放射線〉を創出したい。
[M. N. ]
《ひとつではなく、複数のステイトメントを掲げ、散らす》2019、〈引込線/放射線〉実行委員会
2009年の第一回展からビエンナーレ形式で開催されてきた引込線が十年目の節目を迎えた。名称を〈引込線/放射線〉と変更した本プロジェクトは、設立当初より掲げてきた「ノン・テーマ、ノン・キュレーション」の活動方針を刷新する改革期にある。
残された唯一の枠組みは、既存の制度に拠らないオルタナティブな自主企画展=セルフキュレーションであるということ。本プロジェクトの準備段階では実行委員会を組織して会合を重ね、この枠組みを問い直し、壊し、仮設する作業を幾度となく繰り返してきた。
会合はさながら小さな議会の様相を呈し、実行委員である三十余名の参加者全員が投票権を有して共同体の意思決定に関わる直接民主主義的な体制をとった。プロジェクトにまつわる重要案件は、議案の提出と採決を経てはじめて実行に移すというシステムである。全員が〈引込線/放射線〉を動かしうる権限を持つということ。つまり、ノン・キュレーションは汎キュレーション(pan-curation)の可能性へと通じたのだ。
「緩やかな集い」を前提とする従来の〈引込線〉は、同質性で結び付いた閉鎖的な共同体と見做されることも少なくなかった。しかし実際のところはどうか。「緩やか」という形容は決して正確ではない。異なる思想、異なる背景を持つ者たちの必然性を欠いた集まりは、具体的な問題に直面するたびに、意見の相違、衝突、軋轢といったものを避けがたく生み出してきた。ディスコミュニケーション、付和雷同、宙吊りのまま放置されたアイデア──、負の要素が蓄積するなかで、合意へ到るまでの穏当な手続きが、いつの間にか熾烈な闘争へと転化する。セルフの暴走。綱領なき集団が、各々の目論見を遂行しながら集団性を維持することは果たして可能か。
1909年の創立宣言以降、数多くのマニフェストを発布してきた未来派は、「我々」という主語の扇情的な使用を大いに好んだ。運動の中心人物F・T・マリネッティが目指したのは、伝統的な詩法が依拠する統語法を破壊して「私」なる主語を解体することだった。
他方、過剰なまでに繰り返し用いられた「我々」なる主語は、ひとつの党派の連帯を押し進めると同時に、「我々」と「奴ら」、「味方」と「敵」の分断をもたらした。前衛主義が排他的なエリーティズムに終始するとき、その革命が持ちえたはずの真の波及力は失われる。
「我々」を構成するものとは何か。〈引込線/放射線〉のような綱領なき集団ならば尚更、この主語を無反省に用いることはできない。解体すべきは「我々」という一人称複数形がもたらす有無を言わさぬ拘束力である。
「私」であり「あなた」でもあり「彼/彼女」でもある「誰か」。上下左右の区別もなく、「我々」の強固なまとまりから逃れて幾つもの人称が湧出するとき、分断線は取り払われ、我も彼もが激しく接触する混戦状態が実現する。
個々がセルフィッシュに振る舞いながら、それぞれの卓越性をそれぞれの仕方で追求し、ときには他の誰かの能力を引き出すために連携を仕掛け、(不)自由と(無)責任、緊張と弛緩の極を揺れ動く不断のゲームを進行させること。ルールの形成と破壊を繰り返していく闘争は、やがて一種のスポーツに似たものへと変貌するだろう。
汎キュレーション(pan-curation)の響きから転じてパンクラチオン(Pankration)へ。古代オリンピックの正式種目だったこの格闘技が、目潰しや噛みつき以外なら何でもありの野蛮な競技だったことを記しておこう。あるいはここで、観客と演者の激しい応酬が繰り広げられた「未来派の夕べ」を思い起こしてもよいかもしれない。「夕べ」の舞台では、観客が演者を野次り、果物やパスタを投げつけ、ときに殴り合いの暴力沙汰にまで発展することがあった。「書物に対する体操の優位」を謳った未来派は、幾つかの宣言内にスポーツのメタファーを散りばめている。「未来派の舞台は、我々の競争精神を鍛える競技場となるだろう」(「未来派総合演劇宣言」、1915年)。それから数十年後、美術評論家のH・ローゼンバーグは、抽象表現主義の画家たちのキャンバスを「行為(アクト)する場としての闘技場」になぞらえたのだった(「アメリカのアクション・ペインターたち」、1951年)。アクションの場はこれまでも、地域、時代、文脈、物理的空間を超えて次々とスプリットしてきたのである。
十九世紀後半に興隆した近代スポーツは、ルールを整備することで公平性(フェアネス)を確保し、プロフェッショナル/アマチュア、貴族階級/労働者階級の分断を取り払って参加の機会の平等を促した。著名な社会学者の説を借りれば、近代スポーツの誕生は、暴力が抑制されて社会が文明化していく過程、民主主義的な議会政治の成立と軌を一にしている。スポーツとは元来、戦争に代わる闘争のモデルである。
とはいえ、いくら制度が確立されたところでスポーツの世界に不正や不備はつきものである。同様に、ルールで保証される民主主義的な機構の限界は、〈引込線/放射線〉の小さな議会がたびたび直面してきたことでもある。疑うべきは、公平性(フェアネス)の幻想とあらゆる差異を隠蔽する穏健な個人主義なのだ。安定がどこにもないことを受け入れた上で、闘争のモードを維持しながら、なおかつそのモードを駆動させる基盤自体を批判的に読み替えていく必要がある。スポーツとも芸術とも名づけがたい闘争の場で、〈引込線/放射線〉のプロジェクトは不穏なアクションを続けていくと予告しよう。
闘技場(アリーナ)はひとつとは限らない。シーズンを通じて、複数の場所で、同時多発的に、あるいはディレイを伴いながら、予定調和な筋書きを廃棄した幾つものプレイが実行されるだろう。ひとりのパフォーマーの生身、色面に覆われたキャンバス、印刷物、仮想空間、複数に並立するステイトメントすらも闘争の場となるのだ。そこではルールを逆手にとったぺてんやいかさまが横行し、フィールドに迷い込んだ動物がゲームを中断させ、無法者(フーリガン)の乱入によって暴動が引き起こされることもありうるだろう。数的な強みを活かしたチームプレイと一切の外野を無視した個人プレイを行き来するなかで、勝利と敗北、成功と失敗が重ね合わせの状態で同時に存在することもありうるだろう。
有線、無線、断線、死線。引き込み放射する幾筋もの軌跡。セルフを超えて、保証のない未来に向けて、様々な諸力がひしめく集団的発明物としての〈引込線/放射線〉を創出したい。
[M. N. ]
《ひとつではなく、複数のステイトメントを掲げ、散らす》2019、〈引込線/放射線〉実行委員会